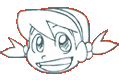|
|
|
|
|
|
■
【ARCHIVE】
「この人に話を聞きたい」 平田敏夫(2) |
―― お作りになっていたCMって、アニメを使ったCMだったんですよね。
平田 そうです。だけど、実写と合成だったりね。一般的なキャラクターを動かすアニメーションもやったけど、あの頃はポップアートがすごい盛んで、ポップアート的なアニメーションを作ったり、オプティカルアート的なアニメーションをやったり。やっぱりコマーシャルの世界って、すごく進んでて、やるものが全部実験アニメーションみたいな感じだった。
―― オプティカルアート的なアニメーションって、例えばどんなものなんですか?
平田 「トヨタサスペンス劇場」という番組のオープニングがあって、それなんか苦労しました。タイムトンネルみたいなところを主観映像でただ突き進んでいく、線と市松模様だけの映像でね。今ならCGでやっちゃうんだけど、そういうものが無い時代だから全部手描きで。
―― タイムトンネルの壁面が市松模様なんですか?
平田 そう。ハイウェイみたいになっていて、それが蛇行すると下のセンターラインが移動したり……。定規で描いたような、クレバーなアニメーション。一方で、横尾忠則、宇野亜喜良、黒田征太郎といったイラストレーターと組んで、そのイラストをそのまま動かしちゃうとか。そういう仕事が、また刺激になった。レナウンの「イエイエ」もそういう仕事だったよね。
―― 「イエイエ」は有名なCMシリーズですよね。
平田 そうですね。僕がやったのは、川村みづえという女性のイラストレーターの画を活かすCMでした。画用紙に水彩で描いて動かしていくような事をするんです。イラストレーションの味を壊さないでやるためには、画力が必要。CMの4年間で覚えた事が結構、財産になってるのかもしれないという気がするんですよ。
―― その後、CMの世界からアニメに戻ってくるわけですよね。
平田 うん。やっぱりストーリーが欲しくなったというのかなあ。CMっていうのは、勿論、長いストーリーがないわけで。
―― 一度CMをやって、アート的な事をやりたいという気持ちは、ある程度晴れたんですね。
平田 晴れてもないんですよ。逆に、欲求不満になっていった。元々「アニメーションで、色んな可能性に挑戦しているのはコマーシャルじゃないか」と思ってコマーシャルの世界に行ったのね。でも、ある時期になるとパターンが読めてきてしまったというか。ある程度覚えしまったら、後はそのアレンジであり、組み合わせをしていく作業になるんです。で、そこで覚えた技術や発想の仕方を、テレビアニメーションや劇場用アニメーションに活かせないのかなあ、活かしてみたいなあと思ったんです。物語世界の中で、そういうような事ができたら面白いだろうなあと思って、また戻ってきたというわけです。
―― なるほど。
平田 コマーシャルも面白かったけど、やっぱりTVや劇場の方に自分の居場所がありそうだなあという気がしたのね。それから、もう1回演出をしてみたいとも思った。コマーシャルでは、自分では演出してないから。
―― CMではアニメーターとしての参加だったんですね。
平田 そうです。スポンサーと代理店があって、ディレクターがいて、という仕切りの中での仕事ですから。CMディレクターになるためには、とんでもなく沢山の勉強をしなくてはいけないし、感覚も鋭くなくてはならない。僕はとても、そちらのディレクターができるとは思わなかった。
―― アニメに戻られてからのお仕事だと、短編『ユニコ』が印象的でした(注5)。
平田 あれは若気の至りというか。
―― そうなんですか。画的な見応えはかなりのものでしたよね。まるで海外の作品を観ているような。
平田 丁寧ないい出来だとは思うんだけど。一番の問題は、僕は何を考えてたんだろうなあ、という事で。手塚さんの原作にそういう部分があったという事で、公害問題みたいな部分を、ちょっとストレートに、生っぽくやりすぎたんですよ。
―― ああ、そうでしたよね。ユニコが、煙を出す工場を壊したりするんですよね。
平田 そうそう。サンリオの社長の辻信太郎さんも「ちょっとまずいよね」と言って(笑)。もうちょっとひねる事はできたよね、と思うんです。だから、ちょっと若気の至り。僕はあれは完璧な失敗作だと思うんです。だから、できれば思い出したくないの。
―― それではサンリオ時代の作品で、よい手応えがあったものは?
平田 サンリオ時代では、その次に作った『ユニコ』。それしかないね。
―― 長編の『ユニコ』ですね。
平田 うん。サンリオの作品だったけれど、制作現場はマッドハウスだった。サンリオ時代には、短編も色々作ったりしたんですけど、辻信太郎さんの想いにどう応えるかという事に汲々としてたんじゃないかな。一応作品らしくなったのかな? と思えるのが『ユニコ』。長いものを演出したのも、あれが最初だし。演出家としての僕は、あそこからスタートしてるのかもしれない。サンリオとしても、実写で「キタキツネ物語」とかは作っていたけれど、アニメーションとしては『ユニコ』が最初の長編だったと思う。
―― サンリオは、人形アニメも作ってましたよね。
平田 はい、ありましたね。あれを作っていた人形アニメのスタッフの方達も、立派なプロの人達で。あの人達と僕らも波長が合って。だから、あちらの作品にも僕はスタッフとして参加させていただいたりね。
―― 設定協力の役職でしたよね(注6)。
平田 そう。イメージボードを描いたりしたの。でも、あの頃の自分の作品としては『ユニコ』しかない。『ユニコ』も、丸山さんが設定として参加していて、彼の力が大きかった。作品に足りない部分を、外から人材を加える事で補充してくれた。構成的に、僕ひとりでやったら弱い部分に村野守美を連れてきたり。美術監督に男鹿和雄を起用したり。作画監督は杉野昭夫ですしね。それは幸せな、人員配置だったね。
―― この場合、村野さんは何をしたんですか。
平田 村野さんは、色んなエピソードを膨らませてくれました。
―― 脚本段階で?
平田 いや、コンテで。
―― コンテ段階なんですか。
平田 うん。脚本はそのままなんです。ユニコーンがペガサスになるときに「変身シーンはこうやった方がもっと面白い」とか。ユニコの相手役として悪魔の子が登場するんですが、「この子はこういう風にした方が、ドラマが広がるんじゃないの」とか。絵コンテという形でサジェスチョンしてくれているんです。
―― 先に平田さんのコンテがあって、それに村野さんが手を入れるんですか?
平田 そうです。
―― 監督が描いたコンテに他のスタッフが手を入れるなんて、随分と特殊なやり方ですね。
平田 マッド作品にはそういうのがいっぱいあります。
―― そうなんですか。
平田 『浮浪雲』もそう。
―― 竜馬暗殺シーンですね。(注7)
平田 それもそうだし、『浮浪雲』では、つまんないとこなんだけど、浮浪雲が新之助と将棋を指して諍いをやるところは、僕がコンテを描いてるし。『夏への扉』も、僕がどこか一部分のコンテを描いてるし。マッドの作品ってそういうやり方をしていたんですよ。
―― あの一時期、そうだったんですね。
平田 そうです。『浮浪雲』も『夏への扉』も、僕は部分参加。そうするのは丸山プロデュースですよ。彼が絵コンテを持ってきて「ここんとこが弱いから、コンテを描いて」って。
―― それはすごいですねえ。
平田 りんたろう作品以外は、結構色んな作品に参加してますよ。
―― それはすごく大事な話ですね。『夏への扉』では、平田さんの役職は演出補佐になっているんですが。具体的にはそういった事をやられていたんですね。
平田 『夏への扉』はコンテは真崎守で、レイアウトに関しては全部川尻がやって、「このシーンはこんな色合いにした方がいいんじゃないか」と私がサジェスチョンしたりとか。
―― そうなんですか。あの作品は、色づかいがかなり大胆で面白いじゃないですか。黒地の背景で、手前に真っ赤な花が咲いていたりするのは……。
平田 ああ〜、あったね。それは川尻のセンスだと思う。僕は、どこかのシーンに関して「赤紫系の薄い色を使うと、ちょっと夢幻的でいいんじゃないかなあ」とか、そういう提案をした覚えがある。作画に関しても「ここは、こうした方がいいんじゃない?」って、原画をいじくった覚えもあるんだ。要するに「なんでも屋」。コンテであったり、色であったり、原画であったり。とにかく色々と手伝う。
―― ものすごく興味がある話なんで、もう少し聞かせてください。マッドハウスの歴史を考えると、出崎・杉野時代が終わって、りんさんが長編を作るようになるまでの数年間がありますよね。
平田 ありますね。
―― それが『夏への扉』や『浮浪雲』、あるいは『ユニコ』みたいな、おいしい作品が続出してる時期なんですよ。
平田 そうそう(笑)。
―― 昔のマッドハウス作品って変わった役職が多いんですよね。具体的な仕事分担が分からないんですよ。「これ、どうやって作ってるの?」みたいなところがあって(笑)。(注8)
平田 あれこそが適材適所だよね。ひとつの作品のひとつのシーンに、突然とんでもない人を丸山が起用する。だから、『浮浪雲』の竜馬暗殺シーンを、村野守美と川尻に「好きなようにやれ」と言って渡すとか(笑)。僕は、どの作品か忘れたけれど、エンディングだけに参加したものもある。僕だけじゃなくて、みんなが好き勝手にのさばってたような気がする。勿論、監督さんはちゃんといて、最終的に選ぶのは監督で、僕らはブレーンとしてアイデアを出す役目だった。
―― なるほど。
平田 今、一番おいしい時期とおっしゃいましたけど、その少し前に『まんが世界昔ばなし』がありましたよね。フリーのりんたろうさんが参加して、川尻もいるし。出崎さんもやってるんだよね。
―― やってますね。
平田 僕のコンテで、川尻がレイアウトから原画まで全部やった作品が、2本ぐらいあるんですよ。あれもマッドハウスのおいしい時代だよね。全て丸山の仕切りなんですよ。「これができるのは、あなたしかいない。だから、あなたやって」という彼のプロデュース。人材のはめ込みの妙というか。未だにそれは生きてるんだけど。
―― そういう仕事をしているのに、あの頃の丸山さんの役職って「設定」なんですよね。「設定って何?」って思いますけど。
平田 そうそう(笑)。丸山のやっている「設定」って、大きく言えば、作品の基本構成なんですね。監督よりも前に、全体のレールを敷く仕事というか。
―― 作品内容とスタッフの両方のレールですか。
平田 いや、最初の頃は、作品作りに魂を入れるためのレール敷きをする仕事で、それを監督に渡す仕事だったんでしょうね。その後、人材派遣までもやるようになったんじゃないかな。
―― ありがとうございます。今日は謎がいくつも解けました。平田さんの『金の鳥』も、そういう体制に近いんですか。
平田 『金の鳥』は、僕は滅茶苦茶、楽しかったんです。あれは演出的な事に関しては、どなたにも手伝ってもらってない。アニメーターを活かした作品なんです。だから、今度は僕が丸山的な立場で、人材を活かすシーンをいっぱい作ったんです。それに関して、演出不在だと言う人もいるんだけど。
―― そうなんですか。
平田 うん。仲間で「あれは演出不在だ」と言う人がいるの。同じように『ボビーに首ったけ』を演出不在って言う人もいるんだけど。
―― 『ボビーに首ったけ』は、演出家の映画ですよ。
平田 そうだよね。『金の鳥』も完璧に演出のワガママ作品だと思うんですけど、見る人によっては、あれは演出不在という風に見えちゃうらしい。あれほどプライベートフィルム的な作品もなかなかないと僕は思うんですけどね。
―― プライベートフィルム的というのは、どちらの事ですか。『金の鳥』ですか、『ボビー』ですか。
平田 両方。それなのに「演出不在だよね」と言う人がいて(笑)。「ええ〜!? 逆じゃないかな」と思うんだけど。
―― じゃあ、いよいよ『金の鳥』の話をお願いします。
●【ARCHIVE】「この人に話を聞きたい」 平田敏夫(3)へ続く
- (注5)
- ここで話題になっている、短編『ユニコ』とはパイロットフィルムとして制作された作品。一般には未公開であったが、後年になって『ユニコ 黒い雲と白い羽』のタイトルでソフト化された。
- (注6)
- 人形アニメ『くるみ割り人形』に、宮本貞雄等とともに設定協力の役職で参加している。
- (注7)
- 『浮浪雲』の坂本竜馬暗殺シーンは、コンテを村野守美が、作画を川尻善昭が担当。鮮烈な映像が話題となった。このシーンの担当に関しては村野守美の名前のみクレジットされている。
- (注8)
- 例えば『ユニコ[長編第1作]』では「設定」の役職で丸山正雄と斉藤次郎が、「設定協力」の役職で村野守美と川尻善昭がクレジットされている。
|
|
|
 |
Copyright(C) 2000 STUDIO
YOU. All rights reserved.
|
|
|
|