|
|

第2回
「『バンパイヤ』――人と獣をつなぐ合成手法」
(バンパイヤ Complete BOX) |
|
氷川竜介(アニメ評論家)
|
|
●超越的な存在“バンパイヤ”
“バンパイヤ”とは本来は吸血鬼のことを指すが、この作品では「動物に変身する人間」とその一族のことを意味する。
定番の狼やコウモリといった猛獣、野獣、禍々しいイメージで彩られた動物への変身譚はホラー映画の伝統芸であった。手塚治虫の原作マンガは、それを虎や大蛇、あるいは猫やキリンにいたるまであらゆる動物に押し広げ、バンパイヤ一族を人間社会に抑圧されたマイノリティとしてとらえることで、闇からの革命のドラマに変えた。
ただし、そのままだと単純な復讐劇になりかねないところに、ロックこと間久部緑郎という明晰な頭脳を奸計にしか使わない第二の主人公を置いたところが、『バンパイヤ』をピカレスクロマンとして一種独特の味わい深い作品としている。ロックは手塚治虫のスターシステムの一人で従来は善玉を演じて来たが、この作品では人間社会とバンパイヤ一族の両方を手玉に取って、自分の欲望のままに支配勢力を強めていく悪の存在として活きいきと描かれている。
名前を見てわかるとおり、彼はシェイクスピアの『マクベス』から材を得ている。だが、ロックの野望とは、ピラミッド型の頂点を登り詰めようという高度成長期の社会人の多くが目ざしていたゴールとそれに対するモチベーションのダークサイドそのものであり、60年代後半ならではの、成長の限界が見えつつある時期の問題意識と表裏一体のものなのだ。
こうした社会性が強いテーマであったことと、折からの特撮ブームに押されるかたちで、手塚治虫の絵柄のままアニメ化するというかわりに選ばれた表現手段が、「実写の人間が動物にセルアニメの変身になる」というものだった。
変身後、実写とアニメは合成されて同一画面で演技を行う。それが最大のセールスポイントのモノクロTVシリーズであった。
●有効な手段として機能した合成
この「アニメと実写の合成」について、文献ではよく「画期的」と記されている。しかし、1968年10月からのオンエアをリアルタイムで観ていた小学生当時の筆者の記憶を引き出すと、新規性よりは「今度はこう来たか」というパズルのピースが埋まるかのような予定調和的感覚の方がむしろ強かった。
1963年に『鉄腕アトム』が放映開始、TVアニメが量産された後に1966年には『ウルトラQ』が児童番組の世界に特撮ブームを巻き起こし、アニメ人気を席巻するという映像文化の流れがある。かくいう筆者も『W3』放送途中から裏番組の『ウルトラQ』に鞍替えしてしまった一人だが、英国産の『サンダーバード』も1966年にNHKで放送され、「人間描写は人形でメカはその分リアルな特撮」という作品まで現れていた。そんな映像媒体が平行してしのぎを削っている時期だから、「空想映像のリアリティ追求とは、自分の成長にあわせて年々進化していくものだ」という強い意識が60年代後半にはうっすらとあった。
それゆえに「人間は実写で狼はアニメ」という発想にしても、「そういうことも映像進化の過程では当然あり得る」というような穏やかな受け止め方があった。こうした認識がどれくらい当時の子どもに一般的だったかは不明だが、筆者としては直後の70年大阪万博が「映像進化の頂点」として強く印象に残っているため、直前に出てきた『バンパイヤ』にしても「変化球のひとつ」というイメージが強いのである。
実際に年表を見ると「実写+アニメ合成」という手法の枠組みでは、1964年にディズニー映画『メリーポピンズ』、1965年にはNHKドラマ『宇宙人ピピ』、1966年には『大忍術映画ワタリ』など近い時期に事例がいくらでも見つかり、この検証も特に合成それ自体が珍しくなく新規性を感じない記憶を裏づける。
だが、『バンパイヤ』という作品それ自体はオンエアされるや充分にショッキングであり、新規の衝撃を抱えていた。だから合成それ自体が画期的なのではなく、むしろ本作の場合は、合成が作中のテーマやドラマなど目ざすものと合致している表現として工夫されていたから、印象に残ったのではないだろうか。こうしたことを、もう少し踏みこんで掘り下げてみたい。
たとえば現在の目で見ると、筆者としては「人間の世界と変身後のバンパイヤの間に超えられない壁が存在する」という絶望的な差異の強調が感じられる。実写とアニメの質感の決定的な違いも、その表現として象徴的に使われているように思える。
人間と動物が超えられない実写とアニメの世界に引き裂かれて描かれているからこそ、子役時代の水谷豊による狼への変身シーンは印象がひときわ強いのだろう。それは、両者の壁を突破するためにその部分だけ格別に手間のかかった手法で制作されているからなのだ。しかも驚きと恐怖を同時にもたらすような、おぞましさを含んだもの……演出意図は明らかにそうした方向性をもっている。
このように考えていくと、本作の作り手たちは「合成すればいいんだ」というような浅薄な発想と意識に汚染されていないと思えて来る。「実写アニメ合成」は、一歩間違えば子どもだまし的な絵にもなりかねない。実際、本作でも第10話「ロック対ルリ子」に登場する「首だけセルアニメの動物に変身した人間」などは、いささかやり過ぎの感もある。だが、全般的には調教された動物を使うなどに比べ、表情豊かなアニメはダークなリアリティを獲得する手段としておおむね有効に機能し、この作品のもつ背徳的で反社会的な空気を大きく支えているのではないだろうか。
●エリアル合成と技法の特徴
では、本作の「合成」とはどのように応用されているのか、技術的な見どころを検証してみよう。
まず、解説書では「エリアル合成」が図解入りで大きく強調されているが、実際のDVDをじっくり見れば、それは手法のごく一部に過ぎないことがすぐわかる。つまり、適材適所を前提とした「手法の複合」が考え抜かれている。
まず、エリアル合成に関しては主にセルアニメの動物キャラクターが実写の人物と「からむ」シーンに使われている。これはエリアル・イメージ・プロセスなどとも呼ばれる一般的な光学合成の手法だ。
虫プロ作品のライバルでもあった円谷プロの特撮映画では、こうした合成には「オプチカル・プリンター」という機材が使われ、雑誌などでも盛んに喧伝されていた。これで実写パートと特撮パートを合成する場合、ブルーに塗られた背景を前に役者が演技することが多い。その映像を現像処理によって白(スヌケ)と黒のマスクに分離し、光学的にフィルム上に未感光の部分をつくり出して多重露光を行うことによって合成する原理のものであった。
これに対してエリアル合成とは、アニメの撮影台の背景が位置するところにコンデンサーレンズを置き、実写フィルムの映像をそこに投影して像を結ばせ、その上にセル画を直接置いて撮影する手法であった。簡単に言い換えれば、「動く実写を背景部分に置いたセルアニメ」ということになる。
これは映像同士をダイレクトにプリントするオプチカル方式に比べ、映写機を通した映像を再撮影するので画質が劣化するというデメリットがある。技術としては一段低いものとなる一方、メリットも多数ある。まず、複数のマスクフィルムを起こす必要がないのでコストが安い。撮影に要する技術も照明の調整などを除けば、通常のアニメ撮影に近接しているから、オペレーション技術の敷居も低い。
オプチカルではフィルムも特別な処理が必要なため撮影後に日数を要し、ようやく届いたフィルムを試写すると「マスクや同期がズレていた」などという、納期間際ではクリティカルなテクニカルエラーの発生するリスクがあるが、エリアルでは撮影台上に合成された状態が視認できるため、エラーが低減できる上に、感光したフィルムも通常撮影のものと同じ納期で仕上げることができる。
こうした理由で映像業界全般にエリアル合成が多用されていた時期がある。アニメ作品でも同時期に放映された(というか『バンパイヤ』2クール目の裏番組になった)『巨人の星』における「飛雄馬のバックに強烈な視線を発する花形が巨大化する」というような大胆な構成の映像などが該当する。CMの分野でも多用されており、東京・五反田にあるイマジカ試写室ロビーには同社が使っていたエリアル合成の実機が役目を終えて静展示されているので、興味のある方は機会があれば見て欲しい(実際、筆者は初めて見たとき見とれてしまった)。
『バンパイヤ』では、たとえばロックがふるったムチを狼トッペイがかわしたり、直撃を受けて悶絶する、あるいは動いている人間ののど元に狼が食らいつくというような、動きと動きがからみあうシーンなどでエリアル合成が大活躍している。これはオンエア当時の印象では、オプチカルに比して自然である上に、実写となじませるために狼の動きが2コマ打ち(一部1コマ)のフルアニメであることが多かったので、「あっ、手を抜いていない!」という新鮮な驚きがあった。
やや蛇足気味だが、小学生当時の筆者はTVアニメの3コマ打ちの動きが手抜きに思えて仕方がなく、「子ども向けと思ってバカにして作っているものをガマンして見てやっている」という気分をいつも濃厚に抱えながら観ていた。『風のフジ丸』のオープニングなどきちんとしたフルアニメの手法でつくられたものを観ているため、手法の違いを正確に知らずとも明解に分けて認識していた記憶がある。だから『バンパイヤ』でも、第2話で狼トッペイが空中へすっとジャンプし、海岸を疾走するときの動きのスムーズさ、尻尾の戻しや脚のバネの説得力に「これはひと味違う」とおおいに喜んだものだ。
ただし、同時に「手塚先生の原作どおりの絵柄じゃないな。なんで『狼少年ケン』とか、そっちに近づけるのかな?」という疑惑も強く覚えていた。今回のBOX解説書で、初めてそれが東映動画時代の大塚康生氏がデザインしたためだと知り、驚愕とともに30数年ぶりの深い納得を得ることができた。アニメ研究は、とにかく奥が深い。
●スチルアニメとその真骨頂たる“変身シーン”
さて、ではバンパイヤ一族が人物や実景と絡むシーンは全部エリアル合成かというと、そういうわけではない。実写部分がFIXなカットも毎回多数に上っており、それらは明らかにスチル写真を背景に置いてセル作画のキャラを上に置く手法でつくられている。これもある種の定番であって、後年の『恐竜探検隊ボーンフリー』(1976)を筆頭にした円谷プロの一連の特撮・アニメ合成作品もこの手法である。
ここでうまいのが、実写部分がスチル写真になってフリーズしたことを極力気づかせないようにする工夫だ。第6話の秋芳洞へ行くくだりでは、通行人が演出的にストップモーションになったところを狼チッペイが駆け回り、そこはスチルで描いておいて、ストップが解けた瞬間からエリアル合成に置き換えている。また、気絶した人間など風景以外にも動かないものは積極的にスチルに置き換えているようだ。
こうした手法の巧みな混用と入れ替えによって、視聴者はあたかも全部がエリアル合成であるような錯覚を与えられる。こうした「うまくだます」工夫が賞賛に値する。
そして特筆すべきは、やはりライブフィルム(毎回の流用を前提としたライブラリーフィルム)にもなっている「トッペイの変身シーン」だろう。ここでは他の場面とはテイストの異なる手法が満載である。
まず、水谷豊の瞳が金色に変化しているのは合成ではなく、金色のコンタクトレンズををはめているからだ。この特殊メイクはライブフィルムの予備動作として撮りきり(処理をしないショットのこと)の本編中でも水谷豊がコンタクトを着用することで、変身カットへの移行をスムーズに見せる効果がある。
変身シークエンス全体は、エリアル合成ではなく「スチルアニメ」の手法で撮影されているのが素晴らしい。これは、撮影したフィルムの連続したコマを動画用紙と同じサイズ(A4とB4の中間ぐらい)の印画紙に引き延ばし、それを1枚ずつアニメの撮影台に乗せてコマ撮りしたものである。
ポイントは写真の上から加筆されたレタッチ(修正・加工)。これによって獣への変身イメージが「絵」として強調されている。実写の人物にみるみる野獣の体毛が群生していくとか、耳が次第に尖っていくとか、うごめく舌の手前にある歯が伸びて牙になっていくといった段階的な変身プロセスが、鮮烈なイメージの映像として実現した。
「狼男」自身は映画の世界ではすでに定番であったが、変身シーンは段階を置いた特殊メイクを数秒単位のOL(オーバーラップ)でつなぐという程度のものであった。『バンパイヤ』の変身は、リアルタイムで生体そのものの特徴が大きく変化していく。これは明らかに後年の『狼男アメリカン』(1981)で描かれたような特殊メイクによる「人狼変身」を先取りしていた。
この変化は写真の上に食いつきの良いセル絵の具で描かれている(またはセルを乗せている)のが高画質のDVDで見るとはっきりわかるが、当時はTV受像器の解像度も低めだったので、本物の体毛や牙を置き換えているようにも見えて、「どうやって撮っているのだ?」と特撮にスレた小学生の筆者にも衝撃度が非常に大きいものだった。
ここでは撮影自体にも、アニメーションとしての工夫がはっきりとこらされていることを強調したい。つまり、セルアニメーションと同様に演出家が撮影シートとフレーム、素材を操作して「撮出し」をした形跡が明瞭に確認できる。実写の人物撮影時には24コマの滑らかなフルモーションであったはずのコマを、おそらく指パラで確認した上で、動きが大きく見えるようにフレームを変えたり、コマを前後させてギクシャクさせているはずだ。間違いなくセルアニメーションを熟知した手が加わっているのである。
また、耳が伸びるショットや変身の最終段階では、「1→2→3→4……」と進むべき動きを「1→2→3→2→4→3→2……」と往復運動に変えて、何度も行ったり来たり撮影することにより、動きに「ビビリ」という微妙な振動を与えるとともに、起きている現象の異常さを打ち出している。
事実、オンエア当時の筆者としても、この不思議な動きが鮮烈に印象に残ってしまって、日常生活の中でも一人になるとアゴをガクガクと動かしながら舌をベロベロさせるマネをして、よく反芻したのを記憶している。
●実写とアニメの世界を往還する作品
「人間」が「実写の世界」でフィルムをスムースに秒間24コマ使って生きているものであり、「動物」が「アニメの世界」で質感をなくしコマを抜いて生きているものだというのが「バンパイヤの世界観」だとしたら、この変身シーンこそはその境界にあたり、両者を混合した手法で、「越境」を表現したものである。
現在のCG映像はリアルとファンタジーを力業でねじふせてなじませようとする方向性にあるが、本当にそれでリアリティが得られるのか、よく疑問に思う。『バンパイヤ』の発想は、両者をはっきりと対立するものとして、まず位置づけている。その上で両者が激しく交わりあい、混沌とする中から映像の驚きが発生し、そこから物語的なダークなテーマが照射される。
この構造は、どんな異常事態も「CGで加工されている」と理解した瞬間に驚きが色あせるようにも思える近年だからこそ再検証が必要で、参考にすべき点の多い作品ではないだろうか。かつて昭和40年代半ばだからこそ荒々しい手法も許され、実写世界とアニメ世界の分断と共存、あるいは往還が描けたのかもしれないが、その時代の味とともに、再見して驚きの多い作品である。
なお、本作には1960年代後半、東京の都市化が完了していない時代の風景が多数写し出されていて、その点でも往時を知る者には大変に古い記憶の数々を刺激する貴重な映像記録となっている。もちろんアニメファンにとっては、前世紀の手塚治虫その人が虫プロダクションの活気あふれるアニメ制作現場の中で写っていることひとつだけでも、感涙ものの貴重さがある。
『バンパイヤ』というのは、こうした数々の点で特別な作品なのである。
|
|
●商品情報
「バンパイヤ Complete BOX」
価格:9975円(税込)
仕様:モノクロ/5枚組(全26話収録)
発売元:コロムビアミュージックエンタテインメント
好評発売中
[Amazon] |
●関連ページ
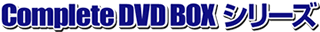
●関連記事
手塚治虫Complete
BOX発売 驚異のブロックバスター!? (05.07.20)
|
|
|